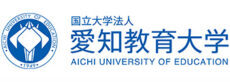2月11日(火)は本学数学教育講座の卒論発表会でした.
今年はタイムマネジメントを意識した分,審査コメントが軽くなってしまいました.同僚の先生ともフィードバック談義させていただきましたが,卒論指導はやはり難しい.
今回の卒論でも気になるのが「先行研究との向き合い方」.孫引きがダメなのは当然ですが「あれっ,先行研究ちゃんと読んでるかなぁ」というのは発表を聞いていてよく感じます.他のゼミの学生が・・・という意味ではなく,自分のゼミ生にも感じるので,自分自身の指導力のなさを痛感します.
「それは先行研究の趣旨と違うのでは?」と指摘されて,修正できるかできないかという能力は指導側の粘り強い指導が必要ですが,先行研究をしっかり読もうとするかは当事者の意識の問題が大きい気がします.
「自分では何度も読んだのですが,そのフレーズをこっちの意味で解釈してしまいました」なのか「表面上のフレーズだけ都合よく抜き出しました」なのか.どっちも「読めていない」わけですが,研究姿勢にはかなり大きな差がありそうです.卒論で「すみません.(先行研究は)サラッとしかみていないです」という発言をどの程度許容すべきかは難しいですね.
ここら辺は,今の3年生(3期生)以降の指導方針をちょっと再検討する必要があるかな.講座の後輩学生の感想を読んでいても「先行研究をしっかり読むべきだと学びました」というものが目にとまりましたが.この「しっかり」の深さの認識が我々と学生の側でずれているのかな?来週の3年ゼミでちょっと聞いてみよう.
石川ゼミ生は無事7名全員が欠席なく発表できました.本人たちの自己評価と他者評価が一致するかどうかは置いておいて,自分的に満足のいく発表ができたのであれば嬉しいですね.自分の研究に悩みすぎて,こんな時間に筆休めで書いてしまった...笑