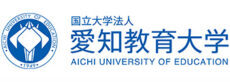今回は「推論主義」に関する発表でした.資料としてはよく勉強していたのが分かりますが,哲学あるあるで初めて聞く学生からすると何を質問したらよいのかわからない,そもそも内容の意味がわからないという事態に陥ってしまいました.とはいえ,これは避けられないところですので,半年後に議論できていればいいかなくらいの気持ちです.
「推論主義」はプラグマティズムの書籍をみても最後の方にある(=発展順序に準じて追っているととてもではないが卒業に間に合わない)という難しさがあります.個人的には,プラトニズム・プラグマティズムという意味解釈の視点自体,普通の教育学部生では触れることもない(最悪,教員生活で意識すらすることなく退職する)ものなのかもしれないと考えています.逆にいえば,だからこそ大学生時代に時間をかけて勉強すべき視点ともいえそうです.
現場の先生とお話ししていると,プラトニズム的な視点とプラグマティズム的な視点が混在しており,それを無自覚に主張する方も多々いらっしゃいます.これ自体は良し悪しはないのかもしれませんが,「(学術的な意味での”研究”ではなく)実践研究」に整理するのであれば,少なくとも意識すべき視点だと思います.そして,これを現場にいる先生に指導したとて,「そんなことどうでもいい(そもそも厳密な”研究”かどうかに興味がない)」「勉強する時間もない(勉強するつもりもない)」といわれてしまうのが目に見えています.だからこそ,大学生時代の勉強が大事なのです.
少なくとも,石川ゼミの学生にはこれを常々伝えているので,ぜひ一緒に頑張っていきたいです.